【DIVERSITY TIMES】わたしって何者? ―外国人二世が語る「日本で生きること」
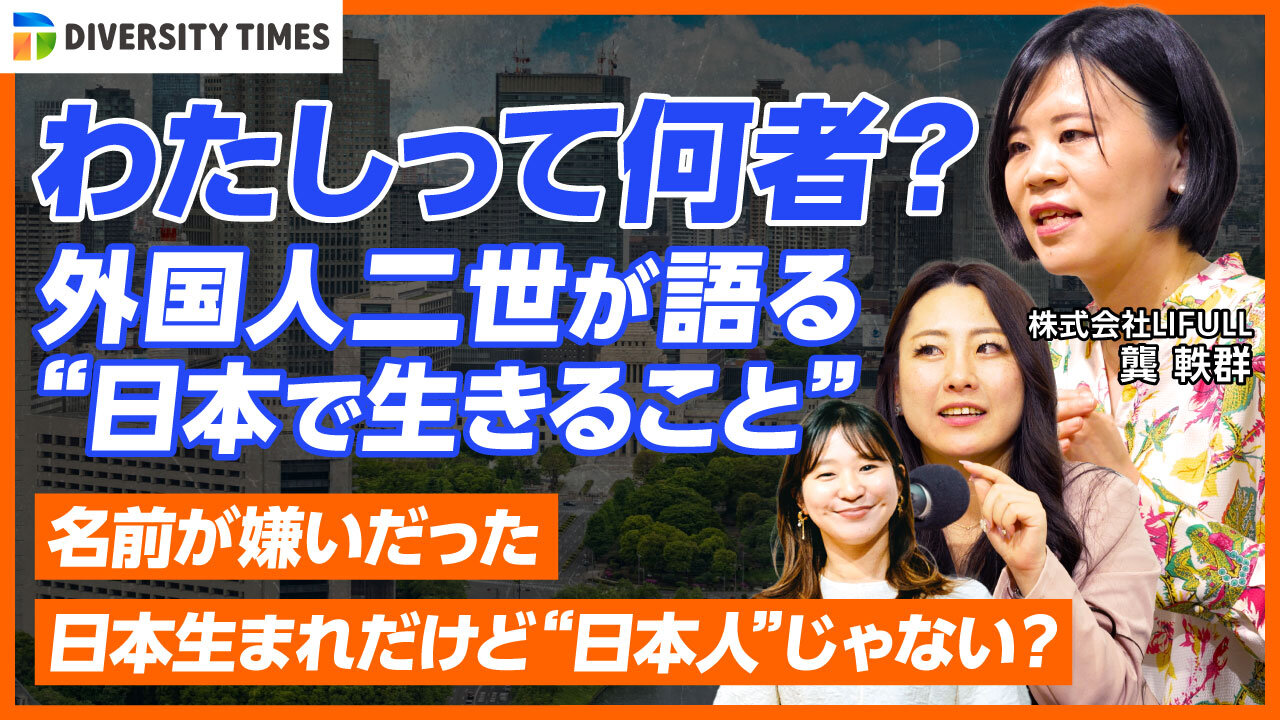
今回は、株式会社LIFULL FRIENDLY DOOR責任者の龔さんが登場。外国にルーツを持ちながら日本で育った「二世」の二人が語る、見えない壁のリアルと、「日本で生きること」への思いを語り合いました。
「外国人雇用」や「多文化共生」がダイバーシティ経営を語る上で外せないテーマとなる中、当事者のリアルな声に触れる機会は、まだ限られています。
今回のDIVERSITY TIMESでは、日本で生まれ育った「外国人二世」にフォーカス。当事者であるお二人に、名前や文化的背景によって直面する「見えない壁」について語っていただきました。
本記事では、YouTube動画「わたしって何者? ―外国人二世が語る“日本で生きること”」の一部を抜粋してご紹介します。
突然ですが、早速みなさんに質問です。
今回のDIVERSITY TIMESでは、日本で生まれ育った「外国人二世」にフォーカス。当事者であるお二人に、名前や文化的背景によって直面する「見えない壁」について語っていただきました。
本記事では、YouTube動画「わたしって何者? ―外国人二世が語る“日本で生きること”」の一部を抜粋してご紹介します。
突然ですが、早速みなさんに質問です。
「日本人でも、外国人でもない」と感じたことはありますか?
・ わたしって何人(なにじん)なんだろう?
・ 名前を言うのが怖い
・ 子どもなのに、親の通訳をしていた(言語ヤングケアラー)
・ 国籍だけで偏見を持たれた
こうした感覚は、おそらく多くの日本人にとって、あまり馴染みがないかもしれません。
でも実はこれ、今回「外国人二世」であるお二人から語られたリアルなエピソード。
今回は、日本社会の中でもあまり語られることのなかった「外国人二世」に焦点を当て、その声に耳を傾けていきます。
・ 名前を言うのが怖い
・ 子どもなのに、親の通訳をしていた(言語ヤングケアラー)
・ 国籍だけで偏見を持たれた
こうした感覚は、おそらく多くの日本人にとって、あまり馴染みがないかもしれません。
でも実はこれ、今回「外国人二世」であるお二人から語られたリアルなエピソード。
今回は、日本社会の中でもあまり語られることのなかった「外国人二世」に焦点を当て、その声に耳を傾けていきます。
ゲストのご紹介
「初めまして、龔 軼群 (キョウ イグン) と申します」
そう自己紹介してくれたのは、株式会社LIFULLで住宅確保要配慮者のサポートを行う「FRIENDLY DOOR」を立ち上げ、現在はその責任者を務める龔さん。
中国・上海生まれ、5歳で来日し、日本で育った外国人二世です。
自身の原体験をもとに、現在は外国籍の方や障害のある方、高齢者など、住まいに課題を抱える人々の支援に取り組んでいます。
今回、もう一人のゲストとして登場したのは、GTN通信部の魯 河廷(ロ ハチョン)さん。韓国にルーツを持ち、日本で生まれ育った外国人二世として、通信インフラを通じて外国人の暮らしを支える仕事に携わっています。
同じ「二世」という立場だからこそ交わせた、等身大の思いと交差する葛藤。
ここからは、お二人の対話から見えてきた「日本で生きること」のリアルに迫っていきましょう。
そう自己紹介してくれたのは、株式会社LIFULLで住宅確保要配慮者のサポートを行う「FRIENDLY DOOR」を立ち上げ、現在はその責任者を務める龔さん。
中国・上海生まれ、5歳で来日し、日本で育った外国人二世です。
自身の原体験をもとに、現在は外国籍の方や障害のある方、高齢者など、住まいに課題を抱える人々の支援に取り組んでいます。
今回、もう一人のゲストとして登場したのは、GTN通信部の魯 河廷(ロ ハチョン)さん。韓国にルーツを持ち、日本で生まれ育った外国人二世として、通信インフラを通じて外国人の暮らしを支える仕事に携わっています。
同じ「二世」という立場だからこそ交わせた、等身大の思いと交差する葛藤。
ここからは、お二人の対話から見えてきた「日本で生きること」のリアルに迫っていきましょう。
「外国人」というだけで直面する壁
外国人「二世」の前に、まず「外国人」として直面する課題から見てみましょう。
たとえば、住まいや金融サービス、スマートフォンなど――
日々の暮らしに欠かせない場面のなかに、「見えない壁」が多数存在しています。
・ 「外国人OK」の賃貸物件が少ない
・ 銀行口座が開けない
・ クレジットカードが作れない
・ スマートフォンが契約できない
背景や条件に関係なく、「外国人である」という理由だけで選択肢が狭められてしまう。
こうした現実は、まだ日本社会のあちこちに残っています。
たとえば、住まいや金融サービス、スマートフォンなど――
日々の暮らしに欠かせない場面のなかに、「見えない壁」が多数存在しています。
・ 「外国人OK」の賃貸物件が少ない
・ 銀行口座が開けない
・ クレジットカードが作れない
・ スマートフォンが契約できない
背景や条件に関係なく、「外国人である」という理由だけで選択肢が狭められてしまう。
こうした現実は、まだ日本社会のあちこちに残っています。
──龔さんのいとこが直面した、「住まい探しの壁」
このテーマに関連して、ゲストの龔さんが語ってくれた原体験をご紹介します。
それは、いとこの一人暮らしの物件探しを手伝ったときのこと。
日本の大学に通い、就職も控えるいとこと複数の不動産会社を回ったものの
「中国の方はちょっと…」と断られるケースが少なくなかったといいます。
それは、いとこの一人暮らしの物件探しを手伝ったときのこと。
日本の大学に通い、就職も控えるいとこと複数の不動産会社を回ったものの
「中国の方はちょっと…」と断られるケースが少なくなかったといいます。

「親戚も日本にいて、日本語も話せて、何かあれば助け合える環境があったのに、
それでも断られた。すごく不条理を感じましたね」
龔さんはこの経験をきっかけに、「住まいの壁」への支援を仕事として取り組むようになりました。
国籍が違うというだけで生じる、「見えないハードル」。
こうした現実があるなかで、「外国人二世」はさらに異なるかたちで壁に直面していきます。
それでも断られた。すごく不条理を感じましたね」
龔さんはこの経験をきっかけに、「住まいの壁」への支援を仕事として取り組むようになりました。
国籍が違うというだけで生じる、「見えないハードル」。
こうした現実があるなかで、「外国人二世」はさらに異なるかたちで壁に直面していきます。
理解されづらい「外国人二世」という存在
次に迫るのは、「外国人二世」だからこそ直面する壁です。
「“二世”って、名前や国籍では”外国人”に見られるから、
理解するのが難しい対象なんだろうなって感じるんです」
たとえば就職活動では、企業が採用の対象として思い描いているのは、「留学生」か「海外からの採用」のどちらかであることが多い。
「“二世”って、名前や国籍では”外国人”に見られるから、
理解するのが難しい対象なんだろうなって感じるんです」
たとえば就職活動では、企業が採用の対象として思い描いているのは、「留学生」か「海外からの採用」のどちらかであることが多い。

「あらゆる場面で丁寧に説明をしないと、
外国人=海外から来たイメージを持たれることが多いんです」
そのたびに「自分は相手が思う外国人でもなければ、日本人とも思われない存在なのだ」と感じる。
その思いは、外国人二世にとって、ずっと抱え続けていく葛藤のひとつです。
外国人=海外から来たイメージを持たれることが多いんです」
そのたびに「自分は相手が思う外国人でもなければ、日本人とも思われない存在なのだ」と感じる。
その思いは、外国人二世にとって、ずっと抱え続けていく葛藤のひとつです。
二世が抱えるアイデンティティクライシス
──「私はいったい何者?」――揺らぐアイデンティティ

「日本人とは言えないし、でも中国人と言うのもハードルがありました」
日本語で不自由なく生活し、見た目も「日本人」と見なされることが多い。
それでも海外に出ると、「自分が何人なのか」に戸惑う場面が何度もあったと龔さんは語ります。
「イミグレでは日本人とは別の”再入国許可レーン“で出国し、上海に行けば“あなたは中国人じゃないわね“と言われ、 日本にいても“日本人じゃない“って見られる。......じゃあ、私はいったい何者なんだろう、って」
日本では、多くの人が当たり前のように持つ「帰属意識」。
でも龔さんは、「自分をどう肯定すればいいのか分からなかった」と学生時代を振り返ります。
日本語で不自由なく生活し、見た目も「日本人」と見なされることが多い。
それでも海外に出ると、「自分が何人なのか」に戸惑う場面が何度もあったと龔さんは語ります。
「イミグレでは日本人とは別の”再入国許可レーン“で出国し、上海に行けば“あなたは中国人じゃないわね“と言われ、 日本にいても“日本人じゃない“って見られる。......じゃあ、私はいったい何者なんだろう、って」
日本では、多くの人が当たり前のように持つ「帰属意識」。
でも龔さんは、「自分をどう肯定すればいいのか分からなかった」と学生時代を振り返ります。
──留学で衝撃を受けた出来事
そんな自分を見つめ直したくて訪れた、上海留学。
「現地で出会った、アメリカの大学に通う中国ルーツの学生に“あなたは自分のことを何人だと思う?”って聞いたんです。そしたら、すごく自然に“私はアメリカ人”って言ったんですよ」
龔さんは、その答えに強く衝撃を受けました。
私は「決して自分は日本人だとは言えない」
育った国によって、こんなにもアイデンティティのとらえ方や名乗り方に違いがあることを、実感した出来事だったといいます。
「現地で出会った、アメリカの大学に通う中国ルーツの学生に“あなたは自分のことを何人だと思う?”って聞いたんです。そしたら、すごく自然に“私はアメリカ人”って言ったんですよ」
龔さんは、その答えに強く衝撃を受けました。
私は「決して自分は日本人だとは言えない」
育った国によって、こんなにもアイデンティティのとらえ方や名乗り方に違いがあることを、実感した出来事だったといいます。
──環境による、ルーツや国籍の捉え方の違い
また日本の教育や文化にも、背景があるのではと龔さんは指摘します。
「日本は“みんな同じ”が良しとされがちで、違いを出すことに抵抗がある。
それが、自分の個性やルーツを肯定しづらくしている気がします」
就職活動など、人生の節目でもこの揺らぎは表れました。
龔さんは、ある就職エージェントから、外国人であるがゆえに「紹介できる案件がない」と言われたこともあったそう。
「自分のことを何も知らないのに、名前と国籍だけで一括りにされる」
そんな思いが、アイデンティティの迷いと結びついていきました。
「日本は“みんな同じ”が良しとされがちで、違いを出すことに抵抗がある。
それが、自分の個性やルーツを肯定しづらくしている気がします」
就職活動など、人生の節目でもこの揺らぎは表れました。
龔さんは、ある就職エージェントから、外国人であるがゆえに「紹介できる案件がない」と言われたこともあったそう。
「自分のことを何も知らないのに、名前と国籍だけで一括りにされる」
そんな思いが、アイデンティティの迷いと結びついていきました。
──二世が抱える「名前」の葛藤
日本人である私にとって特に印象的だったのは、龔さんからハチョンさんへの質問。
「名前を見せるの怖くないですか?」
「驚かれるし、不便だから、なるべく言わないようにしてる」と答えたハチョンさん。電話口では何度も聞き返され、自己紹介の場面では空気が変わることもあるといいます。
「名前を言った瞬間に、空気が変わる。”日本人じゃないんだ”というシャッターが下りる人がいることを経験しているから、怖いんです」
アジア系の見た目の場合、外見からは「日本人」と判断されることも少なくありません。名前にまつわる経験もまた、外国人二世が抱える葛藤のひとつです。
「名前を見せるの怖くないですか?」
「驚かれるし、不便だから、なるべく言わないようにしてる」と答えたハチョンさん。電話口では何度も聞き返され、自己紹介の場面では空気が変わることもあるといいます。
「名前を言った瞬間に、空気が変わる。”日本人じゃないんだ”というシャッターが下りる人がいることを経験しているから、怖いんです」
アジア系の見た目の場合、外見からは「日本人」と判断されることも少なくありません。名前にまつわる経験もまた、外国人二世が抱える葛藤のひとつです。
最後に~「違い」を肯定すること
「人の違いを受け入れるって、実は自分のためでもあると思うんです」
そう話すのは、ゲストの龔さん。
外国にルーツを持つ、子育てをしている、障害がある、性別…
状況次第で、私たちは誰もが「マイノリティ」と呼ばれる立場になることがあります。
そこに対して、人と「違う」ことを否定的に捉えるのではなく、
「違ってもいいじゃないか」と自分自身を肯定してみる。
目の前の人との「違い」に、少しだけ心をひらいてみる。
外国人を「労働力」としてではなく、「一緒に働く仲間」として迎えるために、どのような環境や視点が必要なのか。
そのヒントは、今回のような当事者の声の中にあるかもしれません。
本記事が、制度や支援の「想定外」を見直すきっかけになれば幸いです。
そう話すのは、ゲストの龔さん。
外国にルーツを持つ、子育てをしている、障害がある、性別…
状況次第で、私たちは誰もが「マイノリティ」と呼ばれる立場になることがあります。
そこに対して、人と「違う」ことを否定的に捉えるのではなく、
「違ってもいいじゃないか」と自分自身を肯定してみる。
目の前の人との「違い」に、少しだけ心をひらいてみる。
外国人を「労働力」としてではなく、「一緒に働く仲間」として迎えるために、どのような環境や視点が必要なのか。
そのヒントは、今回のような当事者の声の中にあるかもしれません。
本記事が、制度や支援の「想定外」を見直すきっかけになれば幸いです。
本編もあわせてご覧ください

(リニューアルから新たにつくった「Dポーズ」を一緒に✨)
龔さん、ハチョンさん、ありがとうございました✨
気に入っていただけたら、ぜひYouTubeチャンネルの登録もお願いします📺
今後の配信もどうぞお楽しみに!
これからもDIVERSITY TIMESをよろしくお願いします🌎
龔さん、ハチョンさん、ありがとうございました✨
気に入っていただけたら、ぜひYouTubeチャンネルの登録もお願いします📺
今後の配信もどうぞお楽しみに!
これからもDIVERSITY TIMESをよろしくお願いします🌎
DIVERSITY TIMESとは・・・
テーマは「世界を知り、日本を知り、そして自分を知る。」
多文化共生についての意識を「ニュートラルからポジティブへ変えていくこと」を目指して、外国人や多文化共生をとりまく「いま」を伝える、WOWの特別企画です。

👉前回のDIVERSITY TIMES記事はこちら
【DIVERSITY TIMES】外国人雇用のリアル ― 崩れゆく日本のインフラを守れるか?
【DIVERSITY TIMES】外国人雇用のリアル ― 崩れゆく日本のインフラを守れるか?
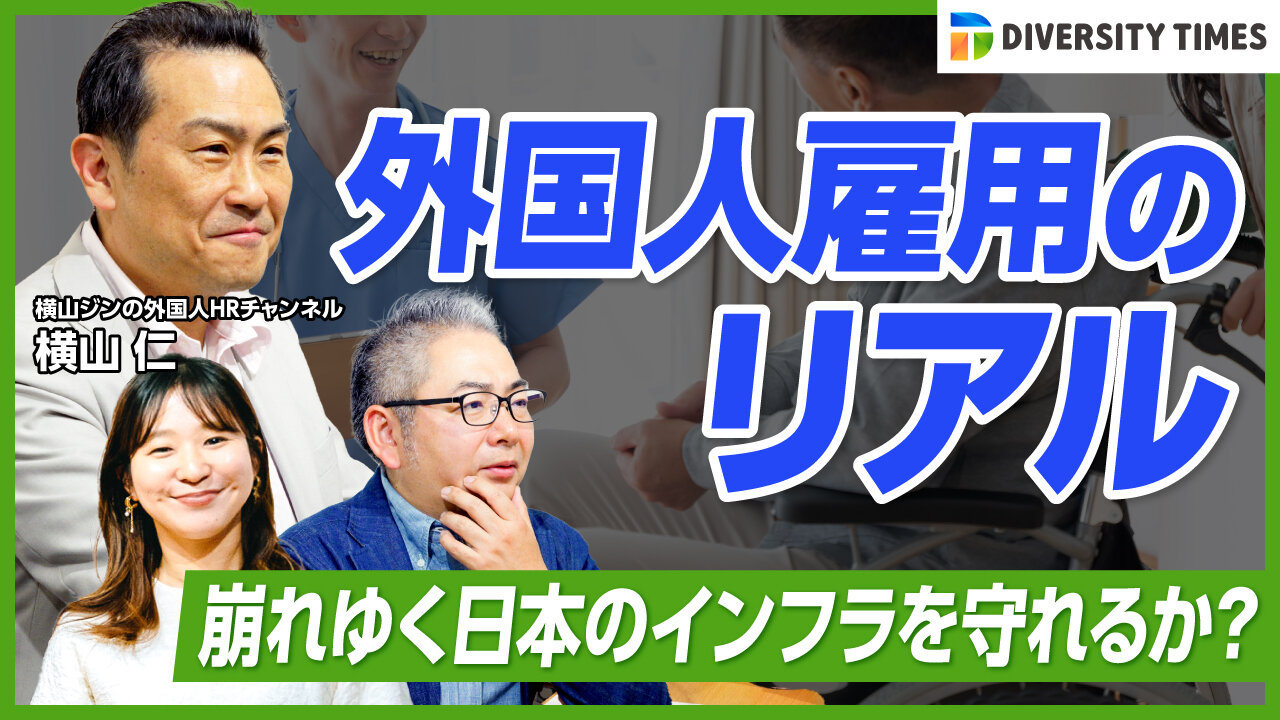






いいね!
エスラ
2025年7月28日
とても示唆に富んだ内容でした。
「外国人二世」という視点から語られる経験や思いは、私たちが当たり前と感じている社会の構造に、静かに問いを投げかけてくれます。
名前ひとつ、言葉ひとつに宿る葛藤は、見えづらいからこそ、きちんと耳を傾けることが必要だと感じました。
多様性とは、単に違いを受け入れることではなく、「見えない壁」に気づき、行動することだと思います。
GTNがこうした声を丁寧に拾い上げ、発信していることに、深く共感しました。
今後も、DIVERSITY TIMESのような対話の場が、多くの気づきと変化につながっていくことを願っています。
素晴らしい企画をありがとうございました。
コメントする